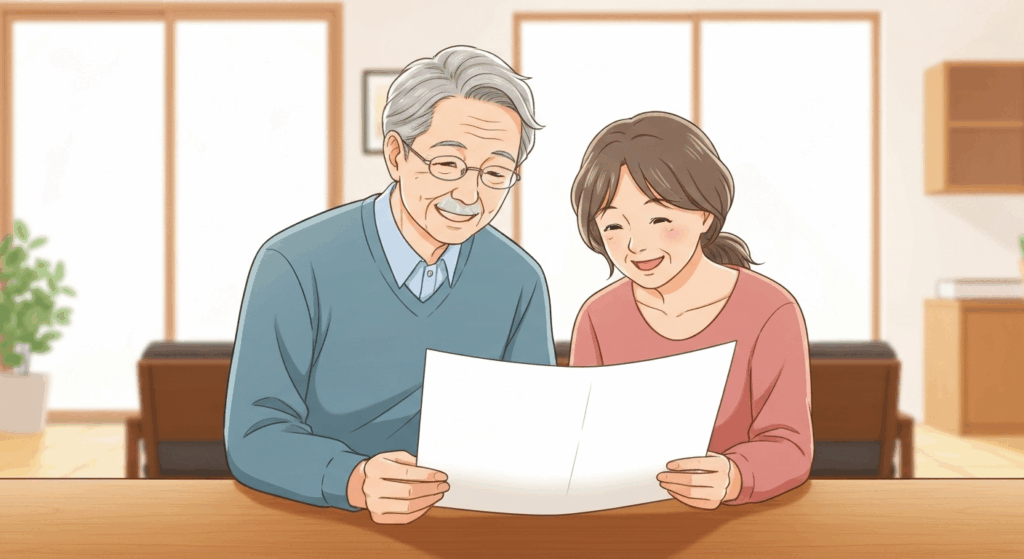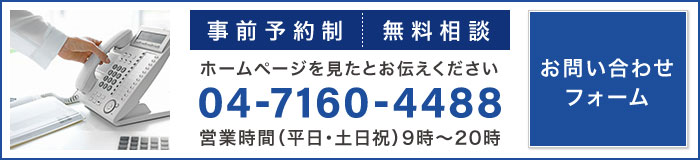このページの目次
「親のもしも…」に、今できる最善の選択は?
「最近、親の物忘れが増えてきた気がする…」「もし認知症になったら、実家の管理や預貯金はどうなるんだろう?」
大切なお父様、お母様の将来を考えたとき、このような不安が頭をよぎる方は少なくないでしょう。ご自身だけで抱え込んでしまうと、どうしていいかわからず、時間だけが過ぎてしまうこともあります。
この記事は、そんなあなたのための羅針盤です。親御様が元気なうちにできる認知症対策の二大巨頭、「家族信託」と「成年後見制度」。一見すると似ているようで、実は目的も使い勝手も大きく異なります。
この記事を読めば、それぞれの制度のメリット・デメリットから、ご自身の家庭にどちらが合っているのかまで、具体的につかめるようになります。私たち司法書士は、法律の専門家であると同時に、ご家族の不安に寄り添うパートナーです。どうぞ、肩の力を抜いて、一緒に最適な道筋を探していきましょう。
家族信託と成年後見制度|3つの選択肢を早わかり比較
まずは、複雑に思える制度の全体像を、シンプルに整理してみましょう。認知症などに備えるための選択肢は、大きく分けて「家族信託」「任意後見」「法定後見」の3つです。それぞれの特徴をまとめた比較表をご覧ください。
| 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 柔軟な財産管理・承継 | 財産管理+身上監護 | 本人の保護(財産・身上) |
| 始めるタイミング | 本人の判断能力があるうち | 本人の判断能力があるうち | 本人の判断能力が低下した後 |
| 財産管理の自由度 | 高い(契約内容による) | 中程度(任意後見監督人の監督下) | 低い(家庭裁判所の監督下) |
いかがでしょうか。「いつ始めるか」「何をしたいか」によって、選ぶべき制度が大きく変わることがお分かりいただけたかと思います。それでは、一つひとつの制度について、もう少し詳しく見ていきましょう。
家族信託:元気なうちから始める「柔軟な」財産管理
家族信託とは、親御様(委託者)が元気なうちに、信頼できるご家族、例えばお子様(受託者)に財産の管理・処分を託す契約のことです。最大の特長は、その「柔軟性」にあります。
例えば、「認知症になったら、この不動産を売却して介護費用に充ててほしい」といった親御様の希望を、契約内容に具体的に盛り込むことができます。これにより、万が一判断能力が低下しても、資産が凍結されることなく、ご家族がスムーズに財産を動かすことが可能になります。
相続対策や事業承継など、積極的な財産活用をお考えの場合に非常に有効な制度です。当事務所代表は(一般社団法人家族信託普及協会による)「家族信託専門士」の認定を受けており、豊富な経験に基づいたご提案が可能です。より詳しい内容は家族信託(家族のための信託)とはのページもご覧ください。
成年後見制度(任意後見):もしもの時の「お守り」
任意後見制度は、親御様が元気なうちに、「将来、もし判断能力が衰えたら、この人(任意後見人)に財産管理と身上監護をお願いします」と、あらかじめご自身で後見人を指名しておく契約です。いわば、将来のための「予約契約」や「お守り」のような制度です。
家族信託との大きな違いは、「身上保護」が含まれる点です。身上保護とは、介護サービスの契約や施設への入所手続き、入院手続きなど、ご本人の生活や療養看護に関する法律行為を代わりに行うことを指します。財産を積極的に活用するというよりは、現状の財産を適切に維持管理し、ご本人の生活を守ることに重きを置いています。任意後見契約の仕組みについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
成年後見制度(法定後見):判断能力が低下した後の「最終手段」
法定後見制度は、すでにご本人の判断能力が不十分になってしまった後に、ご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選んでもらう制度です。つまり、事前の対策が間に合わなかった場合の「最後の選択肢」とも言えます。
注意すべきは、あくまで後見人は家庭裁判所が選任する、という点です。ご家族を候補者として申立てをしても、必ずしも選ばれるとは限りません。財産額が大きい場合などには、司法書士や弁護士といった専門家が後見人に選任されるケースもあります。また、後見人が行う財産管理は家庭裁判所の厳しい監督下に置かれ、例えばご自宅を売却する際には裁判所の許可が必要など、非常に多くの制約が伴います。詳しくは「親の判断力に不安を感じたら… 成年後見制度の利用を検討」のページで解説しています。
【状況別シミュレーション】我が家の場合はどちらを選ぶべき?
制度の概要がわかったところで、次は「我が家の場合はどうだろう?」という具体的な視点で考えてみましょう。よくある3つのケースをもとに、最適な選択肢をシミュレーションします。
ケース1:実家を売却して施設費用に充てたい【家族信託が有効】
【ご家族の状況】
「父は一人暮らしだが、最近足腰が弱ってきた。もし認知症になったら、空き家になる実家を売却して、そのお金で老人ホームに入居してほしいと考えている。父もそれに同意している。」
このようなケースで最初に検討したいのが「家族信託」です。
もし成年後見制度を利用した場合、お父様の判断能力が低下した後にご自宅を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。この許可は「本人の居住用不動産の処分」にあたるため、手続きが複雑で時間もかかります。さらに、「本人の利益のため」という厳格な基準で判断されるため、単に財産を整理したいといった理由だけでは必ずしも許可が下りるとは限りません。
一方、家族信託であれば、お父様が元気なうちに「判断能力が低下したら、長男が実家を売却し、その代金を父の介護費用や施設入居金に充てる」という内容の信託契約を結んでおくことができます。そうすれば、いざという時、お子様(受託者)の判断で、裁判所の許可なくスムーズに実家を売却し、お父様の望む生活のために資金を活用することが可能です。
ケース2:財産管理と身上保護の両方を任せたい【任意後見+家族信託の併用】
【ご家族の状況】
「母は少し物忘れが出てきた。財産の管理も心配だが、今後、介護サービスの手続きや入院手続きなどもお願いしたい。自分は遠方に住んでいるため、柔軟に対応できるか不安だ。」
この場合、「家族信託」と「任意後見」の併用が最適な解決策となることがあります。
まず、不動産の管理や預貯金の払い出しなど、柔軟な対応が求められる財産管理については「家族信託」を設定します。これにより、急な出費にも対応しやすくなります。
そして、家族信託ではカバーできない「身上保護」(介護施設との契約や入院手続きなど)については、「任意後見契約」で備えるといったプランです。
それぞれの制度の良いところを組み合わせることで、財産管理の柔軟性と、身上監護という生活面でのサポートを両立させ、より万全な体制を築くことができます。これは専門的な知識が必要な設計ですので、ぜひ一度ご相談いただきたいケースです。
ケース3:すでに親の認知症が進行している【法定後見のみ】
【ご家族の状況】
「父が認知症と診断され、預金口座が凍結されてしまった。定期預金を解約して入院費用を支払いたいが、銀行から『後見人でなければ手続きできない』と言われてしまった。」
残念ながら、この状況では選択肢は「法定後見」になります。
家族信託も任意後見も、ご本人の「契約を結ぶ」という意思と判断能力がなければ利用できません。すでにお父様の判断能力が失われている場合、これらの契約を結ぶことはできないのです。
こうなると絶望的に感じるかもしれませんが、今からでもできることはあります。速やかに家庭裁判所に法定後見の申立てを行い、後見人を選任してもらうことで、預金口座の凍結を解除し、必要な費用を支払うことが可能になります。手続きが複雑で不安な場合は、司法書士が申立てのサポートをいたしますので、ご安心ください。このケースは、何よりも「早めの対策」がいかに重要かを示しています。
ご自身の状況がどのケースに近いか、イメージできましたでしょうか。もし判断に迷われる場合は、あなたの状況に合った最適なプランをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
【費用で比較】初期費用とランニングコストの大きな違い
制度を選ぶうえで、費用は非常に重要なポイントです。ここでは、それぞれの制度にかかる費用の特徴を比較してみましょう。
家族信託の費用:初期投資で将来の安心を買う
家族信託は、制度設計のコンサルティング、信託契約書の作成(通常は公正証書で作成します)、不動産があれば信託登記の費用など、開始時にまとまった費用がかかります。
金額だけ見ると高く感じるかもしれませんが、これは将来にわたってご家族が柔軟に財産管理を行えるようにするための「初期投資」と考えることができます。一度設定しても、受託者報酬や税務・登記・会計処理などの費用が発生する場合があります。ランニングコストは契約内容や実務対応により変動するため、受託者報酬の有無や負担方法を契約書で明確にしておく必要があります。長期的に見れば、結果的に費用を抑えられる可能性が高いのです。
成年後見制度の費用:継続的に発生する管理コスト
成年後見制度(任意後見・法定後見)は、申立て自体の実費は数万円程度で、比較的安価に始めることができます。
しかし、司法書士などの専門家が後見人(または任意後見監督人)に選任された場合、ご本人が亡くなるまで、家庭裁判所の基準により金額は変わりますが、目安として管理財産額に応じて月額およそ2万円〜6万円程度になることが多い報酬が継続的に発生します(最終的な報酬は家庭裁判所が個別に決定します)。
例えば、月3万円の報酬で10年間制度を利用した場合、総額は360万円にもなります。後見制度が長期化すればするほど、総コストは家族信託の初期費用を大きく上回るケースが少なくありません。どちらがご家族にとって経済的合理性があるか、長期的な視点で検討することが大切です。
家族信託の知られざるリスクと回避策
柔軟でメリットの多い家族信託ですが、万能ではありません。良い面だけでなく、注意すべきリスクも誠実にお伝えします。正しく理解し、対策を講じることで、後悔のない選択ができます。
受託者の負担と責任が重い
財産管理を任されたお子様(受託者)には、信託された財産を適切に管理する「善管注意義務」や、財産の収支を記録する「帳簿作成義務」など、法律上の重い責任が伴います。これが精神的、時間的な負担となり、他のご家族との関係が悪化したりする原因になることもあります。
【回避策】
契約内容を設計する際に、あらかじめ受託者の負担を軽減する工夫を盛り込みます。例えば、受託者に対して信託財産から報酬を支払う定めを置いたり、帳簿作成などを税理士に依頼する際の費用を信託財産から支出できるようにしておくのも1つです。
親族間トラブルの火種になる可能性
特定のお子様だけが受託者になると、財産管理に関わらない他のご兄弟から「財産を勝手に使っているのではないか」「自分にだけ内容を教えてくれないのは不公平だ」といった疑念を抱かれ、争いの原因になることがあります。
【回避策】
契約を検討する段階で、必ず家族会議を開き、なぜ家族信託を利用するのか、どのような内容にするのかを全員で話し合い、理解と合意を得ることが最も重要です。その際には専門知識と豊富な経験をもつ司法書士等を同席させたほうが安心です。また、信託契約書に「信託監督人」として他の親族を選任し定期的に受託者の財産管理をチェックする仕組みを作っておくことや、「受託者は他の兄弟に年1回、財産の状況を報告する」といった条項をあえて盛り込んだりすることで、透明性を確保し、将来の不安を取り除くことができます。
経験豊富な専門家が少ない
家族信託は比較的新しい制度のため、残念ながら、すべての専門家が十分な知識と経験を持っているわけではありません。見様見真似で作成された不十分な契約書では、いざという時に金融機関で手続きができなかったり、税務上の思わぬ問題が発生したりするリスクがあります。
【回避策】
依頼する専門家を慎重に選ぶことが不可欠です。確認すべきポイントは以下の通りです。
- 家族信託に関する相談・組成実績が豊富か
- 「家族信託専門士」などの関連資格を持っているか
- メリットだけでなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明してくれるか
当事務所は、これらの条件を満たし、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案しています。
専門家からのメッセージ:安易な選択は禁物です
最近、家族信託への注目度が非常に高まっていると感じます。しかし、その一方で、制度の仕組みを十分に理解しないまま、「成年後見制度は面倒だから、代わりに家族信託で」といった安易な考えでご相談に来られる方もいらっしゃいます。
私たちは、家族信託を成年後見制度からの単なる「逃げ道」として利用しようとするご相談はお受けしていません。なぜなら、家族信託は思った以上に複雑な仕組みであり、ご家族の状況や財産内容、そして何より「ご本人の想い」に合わせて、オーダーメイドで丁寧に設計する必要があるからです。ご家族のリテラシーや関係性によっては、遺言書の作成や銀行の代理人制度など、他の選択肢をご提案することもあります。
大切なのは、流行りに流されるのではなく、制度の本質を正しく理解し、ご自身の家族にとって本当に必要なものは何かを見極めることです。そのためのサポートを全力で行うのが、私たち専門家の使命です。
まとめ|最適な選択のために、まずは専門家にご相談ください
この記事では、家族信託と成年後見制度について、様々な角度から比較・解説してきました。最後に、大切なポイントを振り返りましょう。
- 家族信託は、元気なうちに始める「柔軟な財産管理」。不動産の売却など積極的な活用を考えている場合に有効。
- 成年後見制度は、財産を守り、ご本人の生活を支える「保護」の制度。身上監護も任せられる。
- どちらが最適かは、ご家族の状況、財産内容、そして何より「どうしたいか」という目的によって全く異なります。
- 安易な自己判断は禁物。後悔しないためには、経験豊富な専門家への相談が不可欠です。
「うちの場合はどうなんだろう?」
「何から始めればいいのかわからない」
そう感じたら、それが相談のタイミングです。一人で悩み続ける必要はありません。小川直孝司法書士事務所では、あなたの不安な気持ちに寄り添い、最善の道筋を一緒に考えます。結論ありきで特定の制度を勧めるようなことはありませんし、相談だけで解決することも多々ありますのでご安心ください。
当事務所は、千葉県柏市中央町5番21号穂高第1ブラザーズビル703にあり、平日は20時まで、土日祝日のご相談も承っております。オンラインでのご相談も可能です。初回のご相談(約30分)は無料ですので、どうぞお気軽な気持ちでお問い合わせください。(代表:小川直孝、所属:千葉司法書士会)