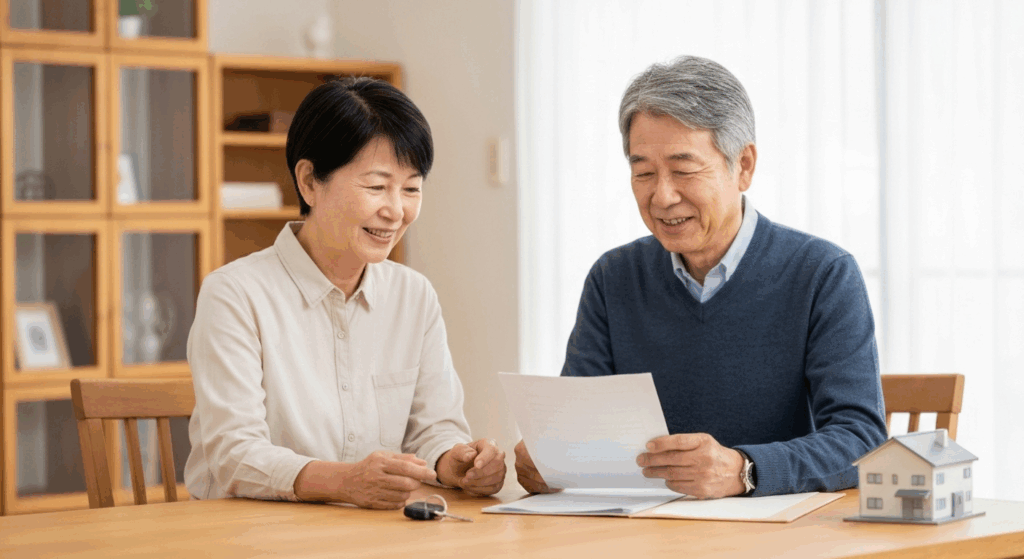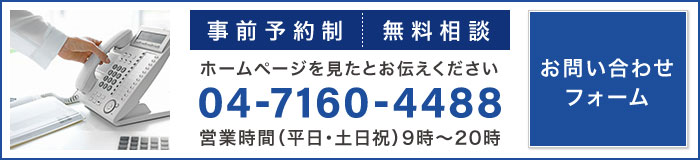このページの目次
法務局へのメールアドレス提供とは?2025年開始の新制度を解説
「最近、不動産の相続登記をしたら、法務局にメールアドレスを出すように言われたけど、これって何?」「個人情報を出すのは少し不安…」
もしあなたが最近、相続、贈与、売買などで不動産の名義変更手続きをされたなら、同じような経験をされたかもしれません。2025年4月21日から、所有権の保存・移転等の特定の登記申請時に、登記名義人の検索用情報(生年月日・メールアドレス等)を申請書に記載して申出できる制度が開始されました。既に登記名義人である者は別途単独で申出することも可能です。
多くの方が、「なぜ急に?」「登録して大丈夫?」と戸惑いや不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。実は、この新しい制度が始まった背景には、社会問題となっている「所有者不明土地問題」を解決するための、ある重要な法改正が関係しています。
この記事では、司法書士の視点から、この新しい「検索用情報の申出」制度について、以下の点を分かりやすく解説していきます。
- なぜ、メールアドレスの提供が必要になったのか?(制度の背景)
- 提供すると、どんなメリットがあるのか?
- 個人情報漏洩などのリスクや注意点はないのか?
- メールアドレスを持っていない場合はどうすればいいのか?
なんとなく手続きを進めるのではなく、制度を正しく理解することで、ご自身の財産を安心して管理するための一歩に繋がります。ぜひ最後までお読みいただき、疑問や不安を解消してください。
なぜ?制度が導入された2つの大きな理由
「そもそも、どうして法務局が個人のメールアドレスを知る必要があるの?」という疑問はもっともです。この制度が導入された背景には、大きく分けて2つの理由があります。それは、「所有者不明土地問題の解決」と、それに伴う「国民の負担軽減」です。
背景①:2026年から住所変更登記が義務化される

長年、日本の社会問題となっているのが、登記簿を見ても所有者が誰なのか、どこに住んでいるのか分からない「所有者不明土地」です。この大きな原因の一つが、不動産の所有者が引っ越しをしても、住所変更の登記がされないまま放置されてしまうことでした。
この問題を解決するため、法律が改正され、2026年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されることになりました。もし、正当な理由なくこの義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
これまで任意だった手続きが義務になることで、所有者不明土地の発生を防ぐ狙いがあるのです。
背景②:登記官が住所変更を自動で行う「職権登記」のため
住所変更登記が義務化されると、「引っ越しのたびに法務局で手続きするのは面倒…」「費用もかかるのでは?」と心配になりますよね。そこで、国民の負担を減らすために導入されたのが「職権登記(スマート変更登記)」という仕組みです。
これは、法務局(登記官)が、市区町村が管理する住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報と照らし合わせ、不動産所有者の住所変更が確認できた場合に、ご本人の申請がなくても自動的に登記簿の住所を書き換えてくれるという画期的な制度です。
しかし、登記簿には氏名と住所しか記録されていないため、同姓同名の方がいると、どの人の住所が変わったのか正確に特定できません。そこで、本人を特定するための情報として、「氏名」「住所」「生年月日」そして「メールアドレス」などの「検索用情報」が必要になるのです。
つまり、メールアドレスの提供は、この便利な「職権登記」をスムーズに行うための重要なカギとなります。
なにをどうする?「検索用情報の申出」制度の概要
では、具体的に「誰が」「何を」「いつ」申し出る必要があるのでしょうか。制度の全体像を整理してみましょう。
提供が必要な「検索用情報」とは?
法務局に申し出る「検索用情報」は、主に以下の4つの項目です。
- ① 氏名・ふりがな
- ② 住所
- ③ 生年月日
- ④ メールアドレス
これらの情報は、登記官が住基ネットの情報と照合して本人を特定し、職権で住所変更登記を行う際に利用されます。また、登記が行われる前には、提供されたメールアドレス宛に事前通知が送られます。
対象となる手続きと対象者
この申出が求められるのは、主に以下のような所有権に関する登記を申請し、新たに不動産の所有者となる方です。
- 所有権保存登記(建物を新築したときなど)
- 所有権移転登記(相続、贈与、売買などで不動産を取得したとき)
対象となるのは、日本国内に住んでいる個人の方です。法人が所有者の場合や、海外にお住まいの方は対象外となります。また、既に不動産を所有している方も、任意でこの申出を行うことが可能です。
メールアドレスの提供は義務?持っていない場合は?
多くの方が気にされている点ですが、申出(検索用情報の提供)は全般的に任意ですが、所有権の保存・移転等の一定の登記申請時には申請書に検索用情報を記載して申出する必要がある場合があります。あくまで任意です。
法務省の検索用情報の申出に関するQ&Aでも、申出は任意であると明記されています。メールアドレスを提供しない場合は、職権登記が行われる際の事前通知が郵送で届くことになります。
また、「そもそもメールアドレスを持っていない」という方もいらっしゃるでしょう。その場合は、申出書のメールアドレス欄に「なし」と記載すれば問題ありません。デジタル機器の利用に不慣れな方も、どうぞご安心ください。
どうなる?メールアドレスを提供するメリットと注意点
メールアドレスを提供するかどうかは、メリットと注意点を比較して判断することが大切です。ここでは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
メリット:住所変更登記の手間と費用が不要になる
最大のメリットは、将来発生する住所変更登記の手間と費用を節約できる点です。
もし、この申出をしない場合、引っ越しなどで住所が変わるたびに、ご自身で法務局へ申請するか、我々のような司法書士に依頼する必要があります。特に、2026年4月からは住所変更登記の義務化(過料あり)が始まりますので、手続きを忘れていると過料の対象になるリスクも考えられます。
一度メールアドレスなどを提供しておけば、法務局が自動で登記情報を更新してくれるため、こうした手間や心配から解放されます。これは非常に大きな利点と言えるでしょう。
注意点①:個人情報漏洩のリスクと法務局の管理体制
「メールアドレスを登録して、個人情報が漏れたり、誰でも見られるようになったりしないか」というご心配は当然です。
まず大切な点として、提供されたメールアドレスなどの「検索用情報」は、法務局の現行の取扱いでは、検索用情報は登記簿(登記事項証明書)には記載されません。ただし運用や将来の制度変更等については公的情報を都度確認してください。
これらの情報は、あくまで法務局が内部で厳重に管理し、職権登記の目的でのみ利用されるものです。国の機関として、強固なセキュリティ体制のもとで管理されますので、過度な心配は不要と考えられます。
注意点②:法務局を騙るフィッシング詐欺に注意
メールアドレスを登録する上で、現実的なリスクとなるのが「なりすましメール」や「フィッシング詐欺」です。
法務局からメールが届くのは、主に「職権で住所変更登記を行いますよ」という事前通知のタイミングです。この仕組みを悪用し、偽の法務局を名乗って個人情報を盗み取ろうとする詐欺メールが送られてくる可能性は否定できません。
被害に遭わないために、以下の点を心に留めておいてください。
- 法務局からのメールで、安易にリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしない。
- メールの内容に心当たりがない、不審だと感じたら、まずは最寄りの法務局に電話で確認する。
- 送信元のメールアドレスが、法務局の正式なドメイン(末尾が「.go.jp」など)であることを確認する。
少しでも「おかしいな」と感じたら、すぐに行動せず、冷静に確認することが重要です。
注意点③:メールアドレス変更時の手続きを忘れずに
意外と見落としがちなのが、登録したメールアドレスを変更した際の扱いです。もしプロバイダの変更などでメールアドレスが変わった場合、法務局へ変更の届出をしなければ、新しいアドレスには通知が届きません。
せっかく便利な制度を利用するために登録しても、肝心な通知が受け取れなくなっては意味がありません。メールアドレスを変更した際には、忘れずに法務局への手続きを行うようにしましょう。
相続登記とメールアドレス提供に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、特に相続を控えた方からよく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. 家族や代理人(司法書士)のメールアドレスでも登録できますか?
A1. いいえ、登録できません。
登録できるのは、不動産の所有者となるご本人が、実際に利用しているメールアドレスのみです。この制度は、法務局から所有者本人へ直接通知を送ることを目的としているため、ご家族や手続きを依頼した司法書士のメールアドレスを登録することは認められていません。
Q2. 複数の不動産を所有している場合、手続きは一度で済みますか?
A2. はい、原則として一度の申出で足ります。
この制度は不動産ごとではなく、所有者である「人」ごとに情報を管理する仕組みです。そのため、一度申し出れば、その方が所有している他の不動産についても、職権登記の対象となります。ただし、登記申請と同時に申し出る場合は、その申請ごとに申出書への記載が必要となる点にご注意ください。
Q3. 亡くなった親名義の不動産を相続します。誰のメールアドレスが必要ですか?
A3. 新たに所有者となる「相続人ご自身のメールアドレス」が必要です。
相続登記は、亡くなった方(被相続人)から、財産を受け継ぐ相続人へ名義を変更する手続きです。したがって、検索用情報を申し出るのは、この相続登記によって新たに所有者となる相続人の方です。亡くなったお父様やお母様のメールアドレスではありませんので、お間違えのないようご注意ください。
まとめ:不安な手続きは専門家にご相談ください
今回は、2025年4月から始まった法務局へのメールアドレス提供制度(検索用情報の申出)について解説しました。
この制度のポイントを改めてまとめます。
- 目的は、2026年から義務化される住所変更登記の負担を減らすため。
- メールアドレスを提供すると、法務局が自動で住所変更登記をしてくれる。
- 提供は任意であり、義務ではない。持っていない場合は「なし」と記載すればOK。
- 個人情報は登記簿には載らず、法務局が厳重に管理する。
- フィッシング詐欺など、なりすましメールには注意が必要。
メールアドレスの提供は、将来の手間や費用を省ける便利な制度ですが、一方で個人情報の管理や詐欺への注意も必要になります。特に、相続登記のような一生に一度あるかないかの手続きと同時に、新しい制度への対応も求められると、不安に感じてしまうのは当然のことです。
当事務所では、こうした法改正の内容も丁寧にご説明し、お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートをご提案しています。相続登記の手続きはもちろん、今回の検索用情報の申出についても、ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。複雑な手続きは専門家にご相談いただくことで、スムーズに進めることが可能です。初回のご相談は無料ですので、安心してご連絡いただければと思います。
事務所名:小川直孝司法書士事務所
所在地:千葉県柏市中央町5番21号穂高第1ブラザーズビル703
司法書士 小川 直孝(所属:千葉司法書士会)