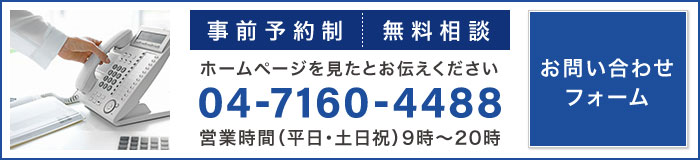このページの目次
相続が発生したら最初にやるべき5つのステップ【初めての方必見】
家族が亡くなったあと、どのような手続きをどの順番で進めればいいのか…と不安な方へ。この記事では、相続手続きで最初にやるべき5つのステップをわかりやすく解説します。相続の専門家である司法書士の視点から、初動の重要ポイントと注意点も併せて紹介します。
- 1. 死亡届の提出と火葬許可
- 2. 遺言書の確認と開封手続き
- 3. 相続人の確定と戸籍収集
- 4. 財産・負債の調査
- 5. 相続放棄や限定承認の判断
1. 死亡届の提出と火葬許可
まず必要なのは、死亡届の提出です。医師の死亡診断書を添えて、市区町村役場に提出します。このとき火葬許可証も同時に申請できます。
提出期限は「死亡を知った日から7日以内」です。遅れないよう注意しましょう。
2. 遺言書の確認と開封手続き
被相続人が遺言書を遺していた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」手続きを行います(公正証書遺言は不要)。
見落とされがちですが、遺言の有無により手続き全体の流れが大きく変わるため、最優先で確認を。
3. 相続人の確定と戸籍収集
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。また、相続人全員の戸籍も取り寄せましょう。
相続人の中に「認知されていた子」や「前婚の子」などがいる場合、見落としが大きなトラブルのもとになります。
4. 財産・負債の調査
遺産には「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金など)」も含まれます。預貯金・不動産・株式・生命保険・ローン・保証債務などをリストアップし、相続の方針を判断しましょう。
不動産は登記事項証明書や固定資産税評価証明書、預金は残高証明書で把握します。
5. 相続放棄や限定承認の判断
相続するかどうかの判断は、「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述が必要です。特に負債が多い場合には相続放棄、プラスとマイナス両方がある場合は限定承認も選択肢になります。
専門家に相談することで、リスクを減らし最適な選択が可能になります。
相続手続きは複雑で、家庭ごとに事情が異なります。迷ったら、まずは無料相談をご利用ください。
関連記事:
相続登記は司法書士に依頼すべき?