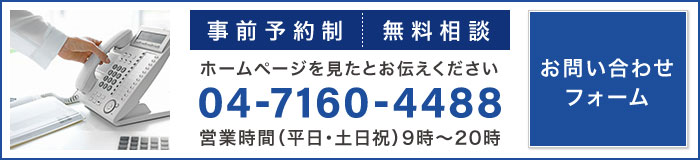このページの目次 相続登記の義務化により、相続人は原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。本記事では、義務の対象となる人、相続人が多数いる場合や行方不明者がいる場合の対応など、注意すべきポイントを司法書士がわかりやすく解説します。 相続により不動産を取得したすべての相続人が対象となります。取得方法には以下のようなケースが含まれます。 一部でも不動産の権利を取得した場合には、登記義務が発生します。 複数の相続人がいる場合でも、登記申請は1人の代表相続人がまとめて行うことが可能です。通常は、以下のいずれかを代表者とすることが一般的です。 代表相続人が申請を行えば、他の相続人も登記義務を果たしたことになります。 相続人が5人、10人と多数にわたる場合でも、登記義務は共有持分を取得した全員に生じます。ですが、全員で登記を行うのは手間がかかるため、代表者に委任する方法が現実的です。 この場合、全員の「相続を証する情報」(戸籍や除籍謄本など)をそろえる必要があり、実務上は司法書士などの専門家に依頼することが多くなっています。 相続人の中に行方不明者や生死不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議や登記申請が進められません。 このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」の申立てが必要です。登記申請には、選任後の管理人が関与します。 行方不明者がいても、義務が免除されるわけではないため、早めの法的対応が重要です。 相続登記義務化により、相続人全員が登記の責任を負う時代になりました。共有持分の取得や行方不明者の存在など、複雑なケースも多いため、早期に司法書士へ相談することをおすすめします。 当事務所では、相続登記義務化への対応をはじめ、各種不動産登記に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。相続登記義務化の対象は誰?相続人の範囲とケース別の注意点
誰が相続登記の義務を負うのか?
代表相続人の決め方
相続人が多数いる場合の対応
相続人に行方不明者がいる場合
まとめ:義務の対象者は実は多い

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。