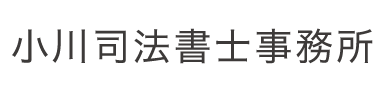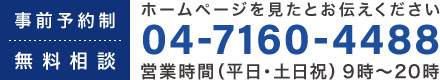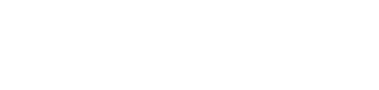このページの目次
家族信託だけでは不十分?任意後見との違いと併用すべき理由
親が認知症になった場合に備えて、家族信託を検討されている方は多くいらっしゃいます。
しかし、実は家族信託だけでは対応できない重要な場面があることをご存知ですか?
この記事では、家族信託と任意後見の違いと、併用すべきケースを分かりやすくご紹介します。
\ こんなお悩みはありませんか? /
- 親の財産を信託で管理しているけど、医療や介護の契約はどうすれば?
- 親の年金やローン付きアパートの管理が信託に含められない…
- 家族信託だけで本当に安心できるのか心配
家族信託と任意後見の基本的な違い
家族信託は主に「財産管理」を目的とする制度です。
一方で任意後見は、本人が判断能力を失った後、法律上の代理権を持つ「任意後見人」が身上監護や法律行為を行う制度です。
家族信託ではできないことの一例
- 病院への入院契約、老人ホーム入所契約
- 年金口座の管理
- ローン付き不動産の借入契約継続
家族信託と任意後見を併用すべきケース
① 信託できない財産がある場合(アパートローンなど)
ローンがついた不動産は金融機関の同意が得られないと信託できない場合があります。
このような場合、任意後見契約を結んでおけば、認知症発症後も任意後見人として財産管理が可能です。
② 年金口座は信託できない
年金が振り込まれる銀行口座は家族信託の対象外。
親が認知症になると、その口座を子が管理することはできなくなります。
任意後見契約であれば、年金口座も適切に管理可能です。
家族信託+任意後見で「安心のダブル体制」
両制度を併用することで、以下のような安心が得られます。
- 信託で管理できない財産も後見でカバー
- 医療・介護契約などの法律行為にも対応
- 将来のリスクに備えた安心設計
※任意後見契約が発効する際は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
まとめ:家族信託だけで本当に足りますか?
家族信託は非常に有効な制度ですが、すべてをカバーできるわけではありません。
任意後見制度と併用することで、ご家族の将来に対する備えが格段に強化されます。