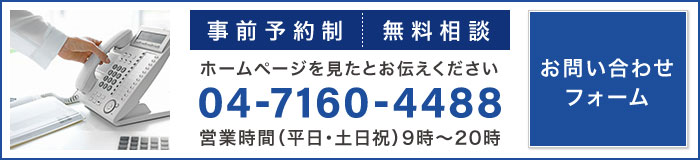2020年7月1日から法務局で自筆証書遺言保管制度がスタートしました。法務省の解説ページはこちら
これは自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局に持参してその原本を保管してもらうという制度です。
このページの目次
【自筆証書遺言保管制度のメリット】
自筆証書遺言保管制度のメリットとしては
- 法務局で保管してもらえることで紛失や改ざんの心配がなくなる
- 法務局で保管されていない自筆証書遺言だと、死後に家庭裁判所での検認手続きが必要になるが、自筆証書遺言保管制度を利用している自筆証書遺言は検認が不要
- 自筆証書遺言保管制度を利用するための手数料は3,900円と公正証書遺言よりも低額
- 自筆証書遺言作成の際や保管制度利用の際に証人が不要
などが挙げられます。
公正証書遺言だと作成費用がかかるので遺言書作成に関する費用を安く抑えたい、という方は検討してみても良いかもしれません。
当事務所では自筆証書遺言保管制度の利用を希望される方のために自筆証書遺言書作成サポートサービス、自筆証書遺言保管申請書作成サポートサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。新型コロナウィルス感染予防の観点からWEB相談(Zoom.Skype)もお勧めしております。
【自筆証書遺言保管制度の注意点】
1.遺言書の作成自体は自分で行う必要がある
自筆証書遺言保管制度を受け付ける法務局は、法律相談を受け付ける窓口ではありませんので、自筆証書遺言の内容についてのアドバイスはしてもらえません。
どのような文章で書いたら良いかとか、誰にどのような財産をどのように遺したら良いか? という具体的な内容にまで踏み込んだアドバイスはしてもらえないということです。つまり、遺言書の内容についてはご自分できちんと決めて体裁を整えたものを法務局に持参しないと自筆証書遺言保管制度の利用はできないことになっています。
たとえば、
- その遺言を実現してくれる人(遺言執行者)を誰にするか
- 祭祀承継者(お墓などを管理していってくれる人)を誰にするか
- 相続税対策や二次相続対策、遺留分対策をどうするか
- もし財産をあげる相手方が遺言する人より先に死亡してしまった場合はどうするか
- 遺言書に書いても良いけど、書かなくても良い内容をどうするのか
- メッセージ的なものも入れたいが可能なのか
等もご自身で決める必要がありますがこれらの要素を入れた方が良いのか入れない方が良いのか、どのように表現すれば良いのかを自分だけで判断するのはなかなか難しいと思います。
このようなことを事前に相談したいという方は、当事務所の司法書士遺言書作成サポートをご利用ください。
2.本人が法務局に出向く必要がある
自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言書を作成したご本人が法務局に出向き、申請書を提出する必要があります。なお法務局の専用予約サイトから申し込みをすることになっています。
このため入院中のため外出ができないとか、老人ホームに入所中で新型コロナウィルス感染予防の観点から外出ができないという方は、この制度の利用は難しいということになります。
3.遺言書を法務局で保管してもらっていることを死後に通知する制度を利用する
自筆証書遺言保管制度を利用する際に、法務局から自筆証書遺言が保管されていることを特定の1人に通知してもらう制度(死亡時通知制度)があります。ただし、この通知は遺言者が希望した場合のみ行われますので注意が必要です。
この死亡時通知がなされない場合は、遺言者があらかじめ親族に「遺言書が法務局に保管されている」旨を伝えておく等しておかないとせっかく手続きをした自筆証書遺言が活用されないことになってしまう可能性があります。
【自筆証書遺言保管制度サポートサービスの料金】
|
遺言書文案作成・遺言書保管申請書の作成 |
50,000円~(税別) ※遺言書に記載する内容によって異なります。 |
|
自筆遺言書の保管申請書の作成のみ |
20,000円~(税別) |
|
印紙代・謄本代・送料 |
実費 |
※申請書に添付する住民票を当事務所で取得代行する場合は1通あたり1,500円(税別)+送料等実費