Author Archive
Zoomセミナーの紹介 弁護士がつたえたい『後見・遺言と信託のちがい』
ふくし信託(株)主催のセミナーの紹介です。
●弁護士がつたえたい『後見・遺言と信託のちがい』
日時:3月13日(水)13:30~1時間程度
開催方式:ZOOM、事前予約が必要、後日視聴も可
対象:障がい児・者のご家族様、福祉関係者等
参加費:無料
参加申込:http://bit.ly/3pBoOo2
申込期限:3月12日(火)9時
詳細 https://civiltrust.com/pdf/20240313.pdf

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度
令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。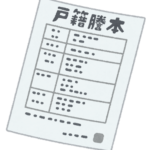
相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。
このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。
ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。
またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。
詳しくはこちら→法務省のパンフレット

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
【千葉県社会福祉協議会】の楽しく学べる!はじめての成年後見講座
千葉県社会福祉協議会で一般の方向けの成年後見講座が開催されるようです。
令和5年12月17日(日) 13:00~15:40
千葉市生涯学習センター2階ホール(千葉市中央区弁天3-7-7)
参加費 無料
「成年後見制度の説明~概要編~」
「成年後見制度の説明~手続き編~」
「要チェック!これだけは知っておきたいポイントは?」
Q&A「成年後見制度笑百科」
クイズ「成年後見制度おさらいクイズ」
後日アーカイブで視聴もできるみたいです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
取締役と欠格事由
会社の取締役と欠格事由については
①一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合
②一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合
を分けて考える必要があります。
会社法331条1項では取締役の欠格事由として次のような場合を規定しています。
| 1 法人 2 削除(=成年被後見人・被保佐人が欠格事由から削除されました) 3 会社法など(以降細かいので省略します)の法律に違反して刑に処せられ執行猶予中の者、執行が終わったときから2年を経過するまでの者 4 前号以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) |
上記の規定から分かること
●会社の取締役に会社がなることはできない。
●会社法などの法令に違反した人は、罰金刑でも執行猶予中でも取締役になることはできない。
また刑の執行が終わってから2年を経過するまでは取締役になることはできない。
●会社法などの法令以外の法令に違反した人は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの間は取締役になることができない。
罰金刑の場合、執行猶予中の場合は取締役になることは可能。
このように会社法関係の罪刑とそれ以外の罪刑とで取締役の欠格事由が異なっています。
以上は一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合の話です。
これとは別に一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合としては
●取締役が破産した場合
民法653条では、委任契約の受任者に破産手続開始の決定があった場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
ただ、上記のとおり破産は取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
●取締役が被成年後見人になった場合
民法653条では、委任契約の受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
こちらも被後見人であることは取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
ちなみに被保佐人であることも取締役の欠格事由ではないため選任は可能です。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
千葉司法書士会による法の日法律相談
毎年10月1日は「法の日」ということで今年も千葉司法書士会で10月初めに県内各所で無料相談会を実施します。
詳しくは千葉司法書士会のサイトを確認してみてください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
NHKに対する受信料支払債務
| 当事務所ではメール・電話での個別の法律相談は受け付けておりませんのでご了承ください。 |
当事務所は司法書士事務所のため、消滅時効援用の内容証明郵便作成「のみ」の業務は行っておりませんのでご了承ください。
NHK(日本放送協会)に対する受信料支払債務についてのご相談(特に時効について)を受けることがありますので基本的事項を整理してみます。
【NHKとの間の受信契約は義務なのか?】
放送法64条1項本文は次のように規定されています。
| 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 |
この規定によれば、NHKとの間で受信契約を希望するしないにかかわらず、NHKを受信できるテレビを設置した人はすべてNHKとの契約締結をする義務があることになります。これは、憲法第29条の「財産権の保障」や民法でいう「契約自由の原則」に反するのではないか?という疑問も生じます。
しかし最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)では、「(放送)法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しない。」として契約締結義務を肯定しました。
⇒NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結する「義務」がある。
【受信契約の義務があるとして、NHKとの間の契約はいつ成立する?】
NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は受信契約の義務があるとして、それではNHKとの間の契約はいつ「成立」するのかが問題となります。
これは、受信料の支払額がいくらになるのかにも影響する問題です。
本人はNHKとの間で契約をした覚えがないのに「契約が成立していました。未納分を払ってください。」ということでは困ります。
この点についても最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には、日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。」としています。
つまり、自分から進んでNHKとの間で受信契約をしていない人に対しては、たとえ受信契約の義務があるとしてもそれだけで契約は成立せず、NHKがその人に対して裁判を提起し確定判決をとることではじめて受信契約が成立するということになります。
また受信契約をしていない人が契約締結義務を履行しないことが履行遅滞による損害賠償の対象になることもありません。
ただしNHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によってNHKとの間での受信契約が成立した場合、NHKが策定し受信契約の内容としている「放送受信規約」によって受信設備(テレビ)の設置の月からの受信料債権が発生するとされていますから、受信料支払義務はテレビ等を設置した月にさかのぼることになります。
【受信料支払債務についての消滅時効はいつから計算する?】
よくご相談をいただくのがこの点で主に「時効援用ができますか?」という内容ですが、
最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、上記契約成立時から進行する。」としています。
これまで見てきたことから分かるとおり、受信設備(テレビ)をいつ設置したかという点がポイントになるようです。
この他にも
・NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は誰か?
・NHKの放送を受信することのできる受信設備とは何を指すのか?
などの事実認定も争われたりするようです。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
障がいのある方のご家族向けオンラインセミナー(ふくし信託株式会社)
7月29日(土) 13:30~15:00
「障害のある方のご家族に知って頂きたい 信託と後見のお話~親なき後の支援及び財産管理を考える~」というテーマでふくし信託株式会社がZoomセミナーを開催するようです。
ふくし信託株式会社は、民事信託の受託者として検討できる法人です。
民事信託では受託者が個人の場合、常に受託者死亡による交代のリスクがありますが法人を受託者にすることができれば安心という側面もあります。
小川司法書士事務所の家族信託のページはこちら

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
不動産取得税
売買や贈与、離婚に伴う財産分与などで不動産の登記名義を取得した人については、不動産取得税の課税対象となります。
居住不動産についての軽減措置の適用により不動産取得税がかからないケースもあるため、そもそも不動産取得税自体について認識していなかったという方もいるようです。
不動産取得税は千葉県内の不動産であれば県税事務所から通知が届くことになります。
千葉県の不動産取得税の軽減措置について(千葉県のホームページ)

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
将来の不安まるっと学べる! 後見・終活講座
6月28日(水)に柏市在住の方向けの終活セミナーがあります。広報かしわ(21ページ掲載)
●時間
①午前10時~正午
②午後1時~3時
●場所 柏市社会福祉協議会 いきいきプラザ
●①②とも先着30人 ※オンライン参加可
●セミナーの内容
①午前10時~正午=法定後見、相続など
②午後1時~3時 =任意後見、遺言、家族信託など
●申込方法 柏市社会福祉協議会に電話(電話番号 7162-5011)

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
成年後見関係事件の概況
2022年1月から2022年12月の間の成年後見関係事件の概況が最高裁判所から公表されています。
●成年後見制度の利用者自体は年々増加していることが分かります。
成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は2022年12月末日時点で合計24万5,087人(前年比約2%増)です。
●興味深いデータとして「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」と耳にすることがありますが、もともと申立書に後見人等の候補者として親族が記載されている割合が全体の23.1%とのことです。これに対し、実際に後見人等に選任された親族の割合は全体の19.1%とのことです。
個人的には申立書の後見人候補者欄に親族の方が記載されていない割合が多いことが意外でした。ちなみに申立書の後見人等候補者の欄を空欄にして「裁判所で適任の者を選任して欲しい」旨を記入すれば家庭裁判所で弁護士や司法書士などの適当な人物を選任することになります。
このデータを見る限り「申立をしても親族が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない」という言葉に間違いはありませんが、親族が選任されない理由はいろいろあるものの、「申立をして親族が後見人等に選任される可能性は低いという訳ではない」ともいえるのではないでしょうか。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。





